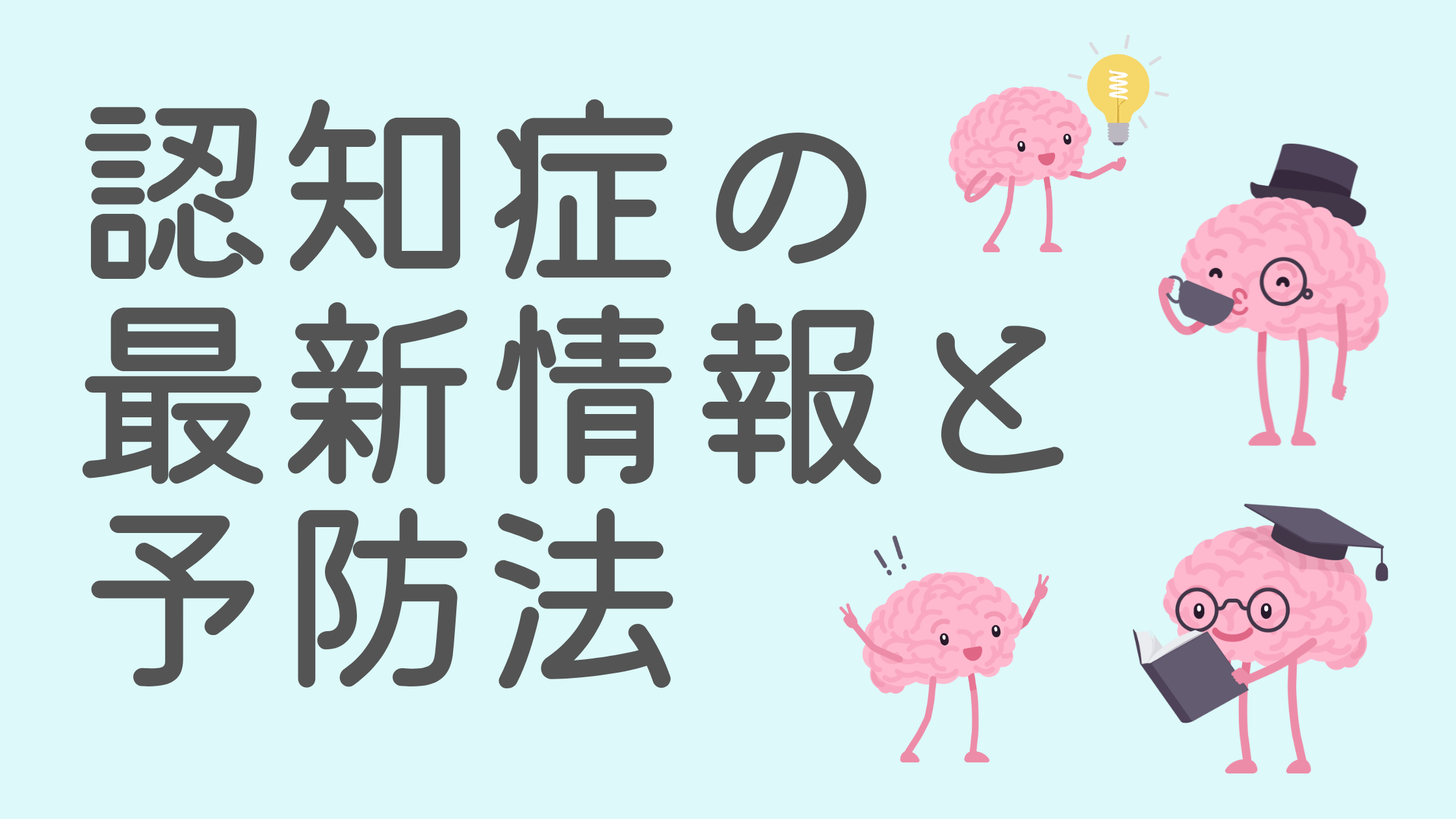こんにちは。終活ガイドのkaoriです。
今回は認知症関連情報を2回に分けてお届けしたいと思います。
先日、医大で開催された「認知症 市民公開講座」に参加してきました。講座は以下の3部構成で、医師・薬剤師・看護師がそれぞれの立場から最新情報をわかりやすく解説してくださいました。
- ① 認知症についての理解と治療の進歩(脳神経内科医)
- ② 認知症のお薬の最近の話題(薬剤師)
- ③ 認知症に備えてしておきたいこと(認知症看護認定看護師)
会場は満席で、市民の皆さんの関心の高さが窺われました。
私も認知症の最新情報を知れただけではなく、日々診療に当たっている医療従事者の方々から医療現場の生の声を聞くことができて安心に繋がりました。

―・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
認知症の現状と社会の動き
「認知症基本法」の施行(2024年1月)
- 認知症になっても**「できること」に目を向け、地域とつながりながら暮らせる社会**を目指す法律が施行。
- 本人や家族だけでなく、社会全体で「新しい認知症観」を共有することが重要。
これは認知症に限らず、障害や困難を抱える全ての人に必要な視点だと感じました。
・共生社会の実現を推進するための「認知症基本法」が2024年1月に施行され、認知症になっても個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」を本人やその家族だけでなく社会全体で持つことが必要とされています。
⇒『できないことではなく、できることに目を向ける』という姿勢、これは認知症に限らず、身体・精神障害等、何かしら困難を抱えているすべての人に対して必要な眼差しではないかと、感じました。
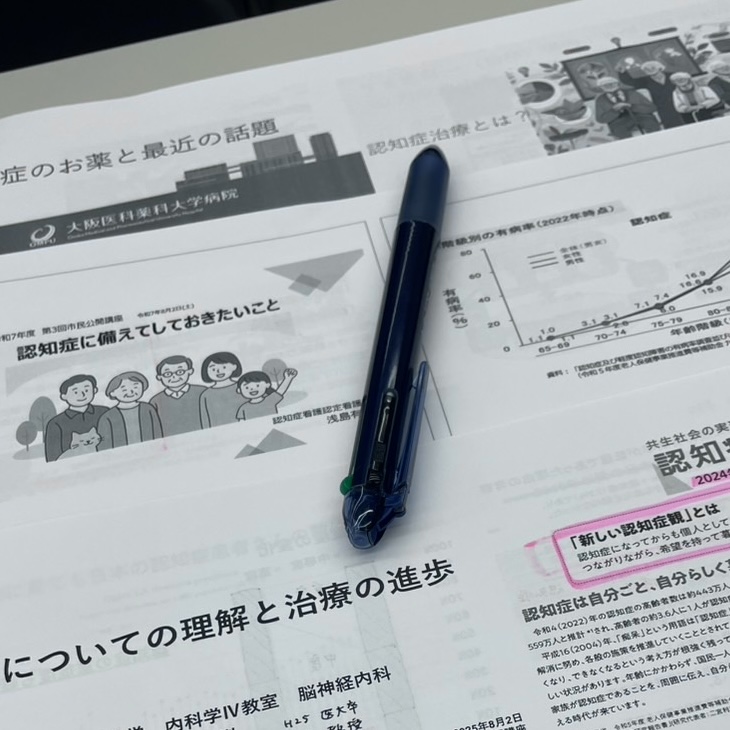
認知症罹患者数の減少傾向
喫煙率低下、高血圧や生活習慣病の改善、健康意識の高まりにより認知機能低下の進行が抑制されている可能性。
しかし、アルツハイマー病による死亡はこの20年で増加しており、治療法の確立はまだ先。
・認知症罹患者数は減少傾向にあり、認知症の重症度も軽減しているそうです。
理由は、喫煙率の低下や高血圧等の生活習慣病管理の改善、健康に関する情報や教育による健康意識の変化などにより、認知機能低下の進行が抑制され、有症率が低下した可能性があるとのこと。
・しかし、他疾患(がん、心不全、脳卒中等)と比べてアルツハイマー病による死亡例はこの20年で大幅に増加しているそうです。理由は認知症の治療法がまだ確立されておらず、対策も遅れているとのことでした。
・認知症予防の新たな知見が得られているが、一方で、認知症発症に関連する遺伝的な素因も明らかになっており、誰もがなり得るという認識が必要、とのことでした。
認知症予防の新たな知見
① WHOが発表した認知機能低下予防の12項目
・身体活動
・禁煙
・健康的な食事
・多量飲酒の減量、中断
・認知トレ-ニング
・社会活動
・体重の管理・高血圧の管理・糖尿病の管理・脂質異常症の管理
・うつ病への対応
・難聴の管理
② アメリカの「ナン・スタディ」から得られた“認知症を回避できた人”の特徴
ナン・スタディ(Nun Study)とはアメリカのカトリック修道女を対象に行われた、アルツハイマー病と老化に関する大規模な縦断的研究のことです。この研究から、認知機能低下の抑制に下記に挙げるようなシスターのマインドが関与していることが分かったそうです。
・感謝する
・赦し(ゆるし)を得る
・執着やこだわりを手放す
・神や大きな流れに委ねる
・他者を頼り、支援を受けることができる力(スキル)
⇒これは私が目指す「かわいいおばあちゃん」になるためのスキルと同じなのでは!?と思いました。
おおらかで、寛容で、とらわれない精神の自由は認知症にも効果があるのでしょうか。
新薬「レカネマブ」と「ドナネマブ」の登場
- 従来の薬は症状改善が中心 → 新薬は病態の進行抑制を目指す「病態修飾薬」
- 軽度認知障害(MCI)の段階で投与することで進行を遅らせる効果が期待される
- 投与方法:点滴、2〜4週に1回、約18カ月間
- 費用:保険適用なしで年間約300万円(1割負担で約30万円)
- 副作用(脳出血など)の可能性もあり、慎重な判断が必要
認知症治療は早期診断がより重要な時代に。MCIは日常生活に支障がないため見逃されやすく、家族の客観的な視点も大切です。
従来の治療は症状改善薬がメインでしたが、新しい治療として期待される病態修飾薬(病態の進行抑制を目指すもの)として「レカネマブ」と「ドナネマブ」の投薬が始まりました。
軽度認知障害(MCI)の段階で投薬すると認知機能低下の進行速度をゆるやかにし、投与中止後も一定期間はその影響が残るとされているそうです。
投薬方法は点滴、投薬期間は2週間~4週間に1回×18カ月程、費用は保険適用がない場合は年間300万円程、3割負担で90万円、1割負担で30万円程とのことでした。また、効果は検証段階であり、副作用(脳出血等)にも注意が必要とのことでした。
認知症治療は早期診断がより重要な時代に入っていますが、軽度認知障害(MCI)は「日常生活に支障が生じていない」と定義される時期のため、意識していないと病院への受診に至らない可能性があるとのことでした。
⇒私の場合、両親と同居しているので様子をよく観察できる環境ではあるのですが、逆に毎日接しているのでその状態が当たり前になっていて気づかないこともあるのかな、と思いました。妹が帰省した際に両親の様子について客観的に観た感想を聞いてみようと思います。
【服薬の注意】
服薬を中断すると無治療の状態まで悪化することが分かっており、3週間以上の中断では中断以前の状態には戻らないとされている、とのことでした。
⇒自己中断せずに、医師・薬剤師・看護師に相談することが大切だと思います。
―・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
認知症への社会的理解と居場所づくり
「認知症」は「痴呆」と呼ばれていたこともあり、何も分からなくなり、できなくなるという考え方がまだ根強く残っており、認知症の診断を受け入れるのが難しいと感じる方もおられるかも知れません。しかし、「認知症」になったことで、急に何も分からなくなるわけではありませんし、できることもたくさんあります。
認知症予防の新たな知見が得られたり、新薬の投薬が可能になったりと、医療も進歩していますが、それと並行して、家族や地域住民の認知症の方に対する正しい理解と優しい眼差し、そして受け入れる姿勢が大切だと感じています。
医師が「認知症になっても、家の中に閉じこもるのではなくて、できるだけ外の世界と繋がってくださいね」とおっしゃっていましたが、社会と繋がることが進行をゆるやかにするなら、認知症の方やそのご家族が気軽に集える居場所がもっと増えたらよいなぁ、と思いました。
終活を学ぶ会のメンバーであるmikaさんがスターバックス堺筋本町店で催されている『よりみちⅮカフェ』の取り組みは、まさにそういう方の居場所つくりです。
まとめ
- 認知症予防には生活習慣の改善と社会参加が重要
- 新薬により早期治療の可能性が広がっている
- 家族や地域の正しい理解と支援体制が不可欠
次回は、終活にもつながる**「認知症に備えてしておきたいこと」**についてお届けします。
関連記事
【認知症予防】WHO推奨5つのポイントと認知症予防10カ条を徹底解説